ブログ
- 2025-12(2)
- 2025-11(13)
- 2025-10(14)
- 2025-09(9)
- 2025-08(10)
- 2025-07(12)
- 2025-06(11)
- 2025-05(12)
- 2025-04(9)
- 2025-03(10)
- 2025-02(10)
- 2025-01(13)
- 2024-12(9)
- 2024-11(12)
- 2024-10(14)
- 2024-09(9)
- 2024-08(12)
- 2024-07(11)
- 2024-06(12)
- 2024-05(12)
- 2024-04(12)
- 2024-03(11)
- 2024-02(14)
- 2024-01(12)
- 2023-12(2)
2025/03/10
【出張】メルボルンの小学校へ

メルボルンの小学校も訪問。
ここではinquiryの授業を見させていただきました。高学年のクラスとファンデーション(1年生の前学年)のクラスを観察。
どちらも非常に興味深かった。高学年の授業では、自分の外側からわかるアイデンティティと自分の内側にしか見えないアイデンティティを氷山モデルに書いていくという授業。多国籍で性別も体格も出自も色々違うのに、このようなトピックをやっていることに感動しました。
また、ファンデーションのクラスは、“I can...”と“I cannot...”を理解する授業。つまり、自分のできる範囲とできない範囲を認知する学習でした。勉強のやり方や成長の仕方を小さい頃から理解するためにとても勉強になる授業でした。
初めて海外の小学校に参観に行ったのですが、教室がカラフルでテンションが上がりました。写真は中庭のものです。
2025/03/07
【出張】ACCEのSusan先生への聞き取り
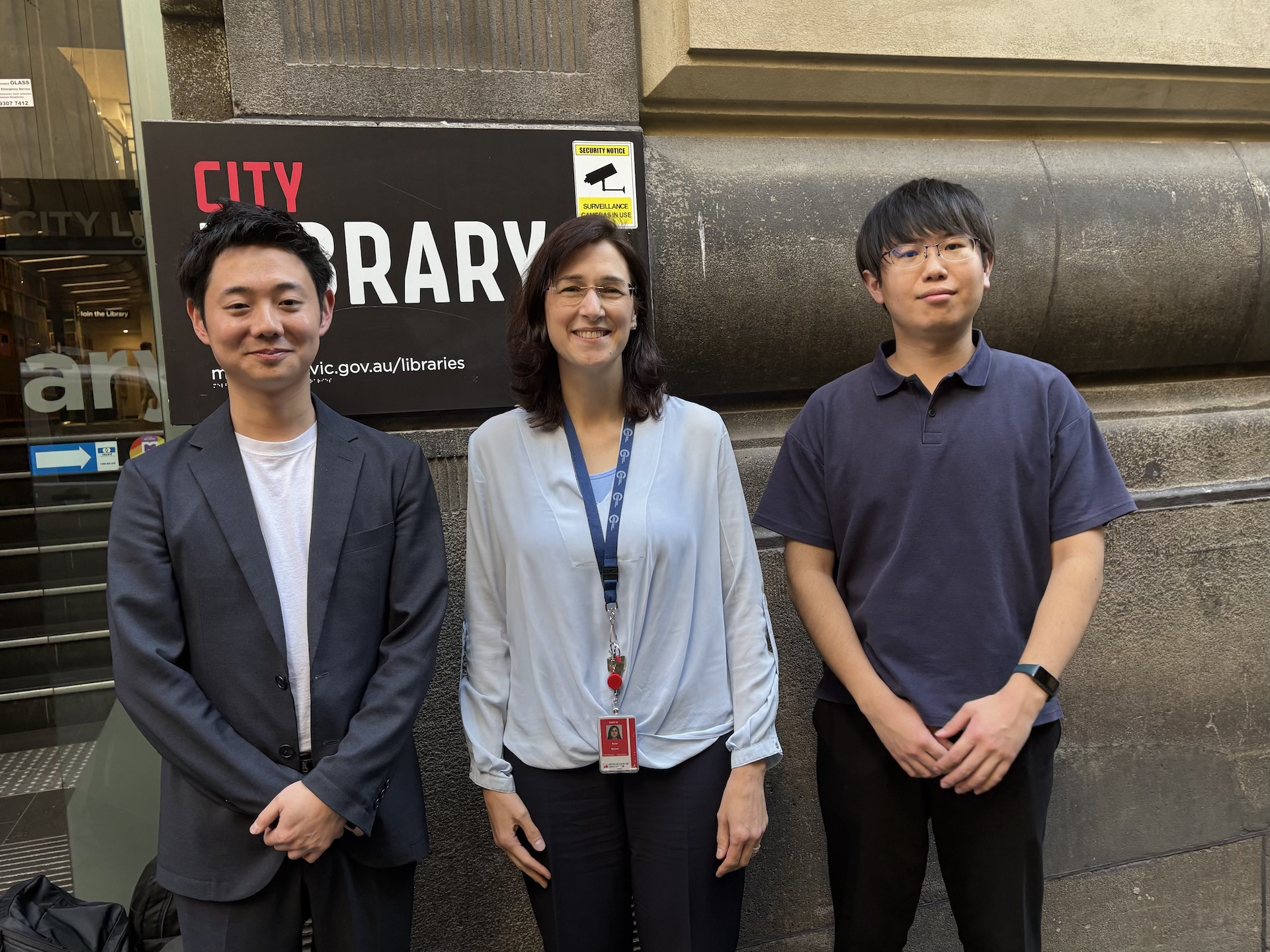
Australian Centre for Careers EducationのSusan先生のもとへ。
ACCEは、以下のサイトが詳しいですが、キャリア教育をできる先生を育てる組織です。
まずは、Susan先生へ私が行っているキャリア教育の科研の成果を報告し、ディスカッションしました。違う理論から価値づけられる可能性をフィードバックいただきました。
その後は、オーストラリアのキャリア教育と日本のキャリア教育の違いについて意見交換。キャリアアシスタンツの必要性を感じながら意見交換をしました。
最後には、嬉しい依頼が。頑張りたいと思います。Susan先生ありがとうございました。
2025/03/06
【出張】メルボルンの中学生への聞き取り

本日は、メルボルンの中学生へ聞き取り。
主にearn and learnやhumanitiesについての聞き取りをしました。
この方は日本にルーツがあり、日本語がペラペラです。またそれだけでなく、説明がとても明快で、具体的に答えてくださいます。
お母様同席のもと、オーストラリアの知りたい情報を知ることができました。本当に感謝しております。
聞き取り後は、お母さんと中学生と私たちで美味しいベトナム料理を堪能。またその後はフォトジェニックなお店でアイスをいただきました。
Mさん、本当にありがとう!またよろしくお願いします。
2025/03/06
【出張】オーストラリアの中学校訪問

本日は、メルボルンにある中等教育学校に訪問。
こちらはアジア系の生徒さんが多い地域でいわゆるオージ(Aussie)は少ないエリアです。といってもその学校は100以上の国にルーツを持つ生徒さんが通っているかなり多様な学校になります。
授業で関心を持ったのは、Year10の歴史の「五族協和」。資料について「資料は何を私たちに教えてくれるか?」「この資料は日本のどんな動機を表しているか?」「なぜこの資料は作られたか?」「五族にどんな影響をもたらす資料か?」を問い、生徒とディスカッションするものでした。
またYear10とYear12のFinanceやBusiness Managementも面白かった。この辺りをどのように意味づけて日本に紹介するのかはとっても難しいところだと思いました。
今回、昼食や学校案内などの高いホスピタリティで温かく迎入れてくださいました校長先生、H先生、C先生本当にありがとうございました。
(写真は校舎内にあったチェスです)
2025/03/04
【出張】 University of Melbourne
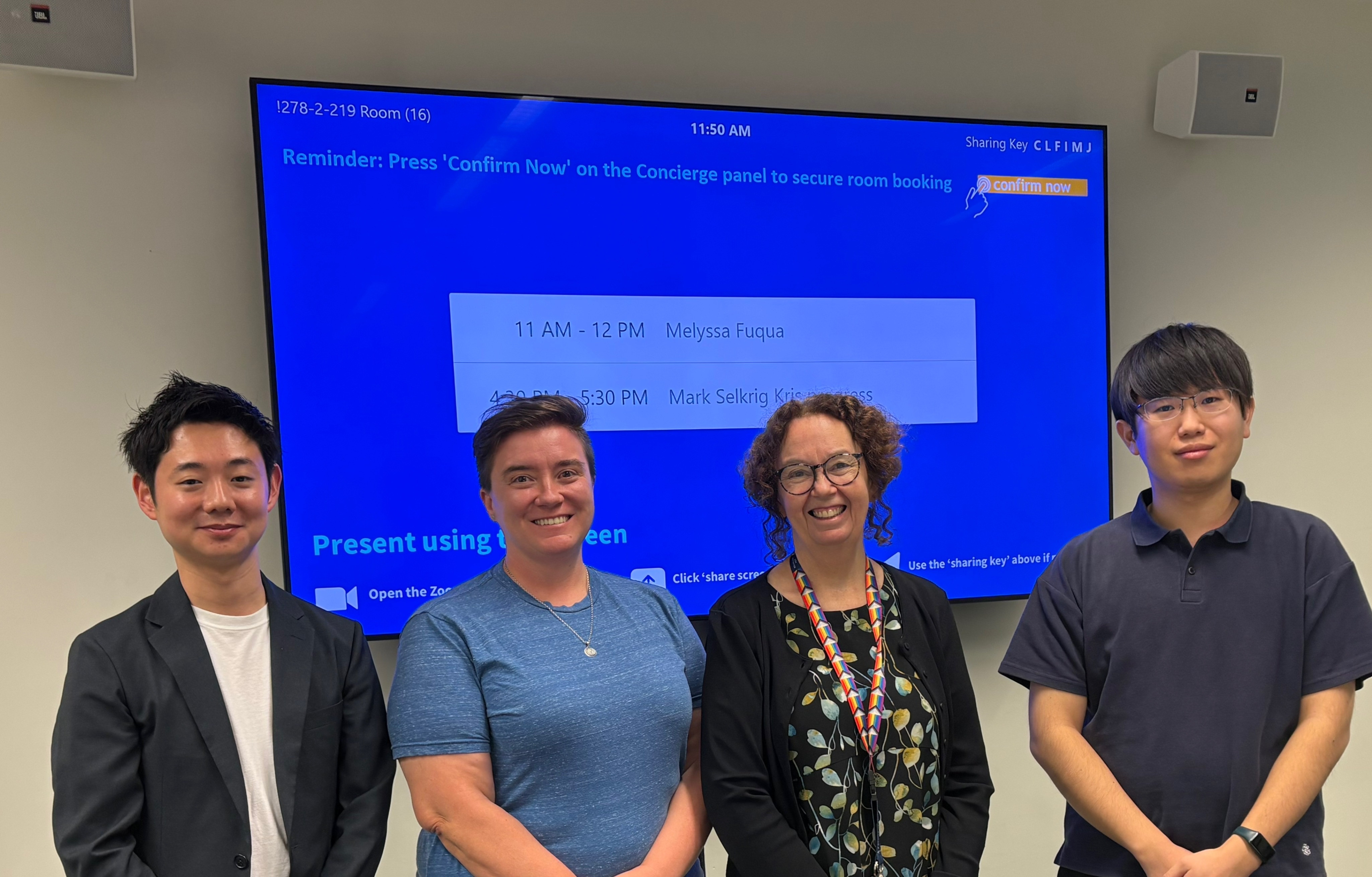
協力者として行なっている科研関係で、オーストラリアのメルボルンに来ています。
いくつかの用事がありますが、本日は両角さん(福山大学)と共にメルボルン大学のSuzanne先生(写真右)、Melyssa先生(写真左)を訪問。
お二人は、キャリア教育について研究をされている先生です。主に「オーストラリアのキャリア教育の制度設計の話」「現在私が行なっているプロジェクト」について意見交換をしました。
本科研は、「日本の社会科教育やシティズンシップ教育の分野では、「職業に必要な力」「お金を稼ぐこと」に対する誤解があるのではないか?」という問題意識から行なっています。本日は、オーストラリアの2人の先生からそうした問題意識に関するヒント、および研究に関するヒントをいただけました。とても充実した時間となりました。
Thank you, Suzanne and Melyssa!

